|
|
 |
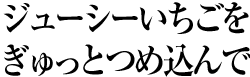 おいしそうないちごのジャムが売られているのは、道の駅「いちごの里よしみ」。ちなみに施設名は、吉見町の特産品であるフレッシュな「いちご」にちなんでいます。 吉見町では、昭和30年代からいちごの栽培が盛んになり、いつしか『吉見いちご』として有名になりました。吉見町は平地が多く水はけが良い土地。甘さがたっぷりつまったいちごが育ちます。 「吉見いちごのいちごジャム」は、1月から5月頃まで収穫される中で、特に完熟期の5月いちごを使ったジャム。いちご・砂糖に、発色を良くする隠し味のレモンを加えれば無添加・無着色ジャムの完成です。 大きめに残った粒はまさに「煮いちご」といった感じ。パンに塗ってつぶしてしまうのはちょっと残念。そのままパクッといきたいくらいです。 |
手作り感あふれるシールがかわいいパッケージ。箱入りはビン2つ入り、3つ入りがあります。 問い合わせ |
 |

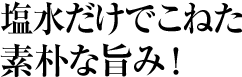 吉見町を含む比企地方の家庭には、何代にもわたって伝わるうどんの打ち方があります。それは武蔵野台地で育った地粉を塩水だけでこね、「手で丸めてから足で踏む」少々乱暴なやり方。これで「素朴で力強い」男前のうどんができあがります。と言っても、うどん打ちは家事の一つなので女性も積極的に参加。結婚式などの祝いの席で振る舞われることが多く、おばあちゃん世代までは、打ち棒は嫁入り道具でした。年越しそばのようなはっきりした理由はありませんが、ハレの日に欠かせない、どことなく縁起の良いうどんです。

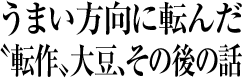 小耳に挟んだ話では、減反政策で転作して大豆に取り組むケースは珍しくないとか。そこで沢山できた大豆をどうするかが各まちの悩みどころ。場合によっては厄介者扱いされることも……。 吉見町でも転作大豆が作られていますが、こちらの大豆は味噌に化け、人気者の地位を獲得しているようです。米味噌と麦味噌があり、それぞれ地元産の米・麦との組み合わせ。味噌に向いていると評判の地元産大豆「ナカセンナリ」を使用しています。 味噌作りは、発酵のための温度管理が一番の難関。真冬の夜中に湯たんぽを置きに行くこともある、という味噌作り名人は、地元専業農家の主婦の皆さん。手塩にかけて育てられた味噌は1年熟成され、2歳になった頃に旅立っていきます。

古墳時代後期に作られた横穴墓群。戦時中に地下軍需工場の建設のために数十基の横穴が壊されてしまいましたが、その後の地元住民の管理によって、現在も219個の横穴が保存されています。百穴には国指定天然記念物である「ヒカリゴケ」が生息しています。ヒカリゴケは、森林内の湿地に生えるめずらしい植物。レンズ状の細胞がつながってできている原糸体と共に生えているため、光線を屈折反射し、緑色に光ります。

交流拠点施設として最近人気の「道の駅」。名前の通り、「いちごソフトクリーム」や「いちご大福」が販売されています。施設内には農産物直売施設や食事処の他に、芝生広場、アスレチックなどもあり、買い物ついでに遊んで帰れる、一石二鳥な道の駅です。

|
 岩の側面に、細長い穴がいくつも掘られた「吉見百穴」。この不思議な史跡は、今から200年ほど前に既に文献に見られ、江戸中期には「百穴」の呼び名が付いていたとか。明治以降、科学的に検討が始められ、土蜘蛛人(コロボックル)の住居だったという説が一時期定説になりました。大正時代にはその「住居説」は覆され、墓穴であることが確定されましたが、百穴を眺めていると今にもコロボックルがひょっこり顔を出しそうな、和やかな雰囲気がこの町にはあります。 百穴の中で、キラリと光るのはヒカリゴケ。控えめな輝きはこの町らしさの象徴。吉見町の味も、和みの中にキラリとおいしさが光ります。 吉見町
吉見町商工会
総面積 38.63平方キロメートル |

