|
|
 |
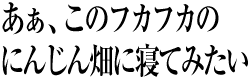 寒さが本格的になってくる12月頃、朝霞市内を歩いていると、ふわふわっとしたパセリに似た葉で埋め尽くされている畑を頻繁に目にします。細い畝に並んだ葉っぱがふわふわ、ゆらゆら。なんだか暖かそう。あの上で寝てみたい、という衝動にすらかられるこの畑は、にんじん畑です。 朝霞市は冬にんじんの産地。東武東上線の朝霞台駅前にも、にんじんのオブジェが置かれているほどです。 実は、朝霞のにんじんには冬場の土ぼこり対策として作られている、という役割も。関東ローム層特有のほこりっぽさを、にんじんの葉が抑制してくれているそう。青々とした葉っぱの意外にお役立ちな一面を見た気がします。 注目のボディは、オレンジ色も鮮やか。そのまま色を活かして調理したい、ぽっちゃり美人なにんじんたちです。 |
市内には、直売所のほかにも「庭先販売直売所」という、農家の直売所が多数。朝どりの新鮮にんじんが、驚くほど安く手に入ります。 問い合わせ |
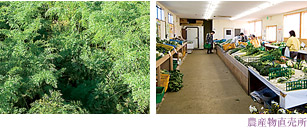 |

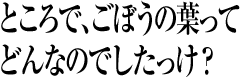 第1問。「土にまみれた細長いその姿から、ごぼうの葉を想像してみてください。」 なんとなく細長い、笹のような葉? 正解は、ごぼうの右下をご覧あれ。意外にも、ごぼうの葉は割と丸い形をしています。朝霞市内には、この葉が繁る畑が点在。 では、第2問。「ごぼうの収穫動作を再現してみてください。」 へっぴり腰で、よっこらしょ? 不正解。ごぼうは土の奥深くまで根を伸ばしているため、とても人力では収穫不可能。専用の掘削機で掘り上げるので収穫の様子はなかなか見られません。 そんなことを想像してごぼうを見てみると「よく出てきたね」と誉めたい気持ちになってきます。地上に出てきても土臭いのは、地中の生活が長かったせい、と勘弁してあげてくださいね。

1680年代(江戸時代中期)よりも前に造られた、茅葺屋根の民家です。埼玉県内と言わず、関東ではかなり稀少な建物。主屋は重要文化財で、ほかに倉・納屋などの建物や屋敷林も一緒に保存されており、武蔵野台地のスタンダードな農家の構成を伝えています。これが、江戸時代から続いている朝霞の原風景です。

「岡城」という城跡に作られた公園。黒目川を望む台地を利用した城で、今でも空堀や土塁が残っています。発掘調査の結果から、戦国時代に築かれたものであることは判明していますが、城主は不明。現在は公園として整備され、春の桜や夏の新緑を楽しみに、多くの人が集まる憩いの場となっています。

|
 「朝霞市」とは皇族の朝香宮殿下に由来して名付けられたもの。昭和5年(1930年)に東京府世田谷にあった「東京ゴルフ倶楽部」がこの地に移転した際の町制施行をきっかけに、当時倶楽部の名誉会長だった朝香宮様の名前をいただき、一文字変えて「朝霞市」となりました。 それ以前は、旧石器時代から人が住み、大きなクニがあったり、新羅人の集落「新羅郡」が置かれたりと、様々な変遷がありました。 また、最近の情報としては、川越街道の膝折宿として栄えてきた歴史もあったりと、いつの時代もにぎわいを見せている朝霞市は、土壌が豊か、水も豊かな恵まれた土地です。春夏秋冬、どの季節にも市内の畑には瑞々しい野菜が育っています。 朝霞市
朝霞市商工会
総面積 18.38平方キロメートル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
